辻仁成の小説『サヨナライツカ』は、その耽美な作風と愛憎渦巻く物語構成によって日本の文学シーンにおいて高い評価を受けた作品の一つである。後に中山美穂と西島秀俊という実力と魅力を兼ね備えた俳優陣によって映画化されたこの物語は、単なるロマンス映画や不倫映画の枠を超えて、時代背景や社会的文脈を鑑みることで理解を深めるべき重厚なテクストとして再発見される。本稿では、「サヨナライツカ」という作品が1970年代のバンコクを舞台に、婚約者を持つエリートビジネスマン・豊と謎めいた美女・沓子との不倫関係を軸に描かれる中で、当時の社会背景、異国情緒、そして不倫というテーマに込められた作者・辻仁成のアプローチについて批評的な目線で考察し、映画化に際して見えてくる特徴、さらには他の不倫作品との比較を通じて、本作が示す文化的意義や時代性を解説していく。
経済成長する日本を暗示した登場人物
まず、『サヨナライツカ』というタイトルが示唆するように、本作は単なる別れの物語にとどまらず、「いつか」訪れるであろう別離の瞬間を内包した上での燃え上がる愛を描いている。舞台は1975年、東南アジアのハブ都市としての存在感を増しつつあったバンコク。高度成長期を経て国際社会に積極的に関与し始める日本企業が、当時、東南アジアへ進出していた史実的背景を踏まえると、本作において豊がエリートビジネスマンであることは偶然ではない。主人公は企業戦士として国境を超え、海外で日本のビジネスを拡大する役割を担う存在として描かれるが、その一方で、彼自身が愛というプライベートな問題に深く足を取られていく過程は、日本経済と社会が多様化する中で生まれつつあった新たな価値観の揺れ動きを象徴している。
物語に登場する豊は、婚約者が本国にいるにもかかわらず、バンコクのホテルで出会った謎めいた女性・沓子に惹かれていく。ここで重要なのは、単純な浮気や気まぐれな恋ではなく、互いがどこか満たされない魂を抱え、出会いという偶然をきっかけに、空虚を埋めるようにして求め合う点である。1970年代という時代は、国際化が進む一方で、まだどこか「愛」や「結婚」というものに旧来の規範が強く残っていた時代でもあった。当時、不倫という行為は現在以上にタブー視され、社会的制裁や道徳的非難を招くものであったが、本作はそうした規範を前提としながら、男と女が何故そこまで禁忌を犯してでも求め合うのか、その背後にある人間の欲望や不安に踏み込み、当時としては相当に挑発的なテーマ提示を行っている。
作者が持つ普遍的な、光と闇、相反するテーマ
この挑発的テーマは、作者である辻仁成自身が持つ文学的特徴とも呼応する。辻は時に光と影、生と死、愛と破滅を往還するような作風で知られており、『サヨナライツカ』もまた、「死」という言葉が直接的に語られるわけではないが、常に別れや時間の有限性が存在感を放っている。「いつか」終わりが来る愛にすがる二人は、ある意味で、たった一度の人生を賭けた挑戦者でもある。その対象が不倫であろうが、世間の目があろうが、人間的な欲求を優先する二人の姿から立ち上がるのは、愛の崇高さや汚れを超えた本質的な渇望だ。
映画化にあたり、中山美穂と西島秀俊というキャスティングは極めて象徴的だ。中山は日本のトップアイドル出身でありながら、女優として多彩な表情を見せてきた一方で、海外生活の経験もあり、その存在自体がある種の国際性や異文化への開かれを感じさせる女優である。彼女が演じる沓子は、謎めいた美女であり、その正体や内面は簡単には掴めない。中山美穂の持つミステリアスな魅力と、儚さ、そして可憐さが、この沓子というキャラクターに深みを与え、バンコクという異国情緒を帯びた背景の中で輝く存在として成立している。
西島秀俊が演じる豊は、寡黙さと内在する情熱を両立したキャラクター表現で知られる彼のフィルモグラフィを踏まえると、適役といえる。理性的な社会人としての表情と、抑圧された欲望が噴出する瞬間の表情、この二つを西島が巧みに演じ分けることで、不倫関係に陥るエリートビジネスマンの苦悩がリアリティを伴って伝わってくる。こうしたキャストの妙は、日本映画界が描く異国での不倫劇に真実味と詩情をもたらし、観客は単純な不貞行為を目撃するのではなく、人間存在の奥深い葛藤を目の当たりにすることになる。
1970年の空気=生き物としての人間
本作の見どころの一つは、1970年代という時代設定が醸し出す独特の空気感だ。現代のようにスマートフォンで即時連絡が可能な時代ではなく、旅先での出会いや別れ、そして国境を越えた関係性はより一層、ドラマ性が際立つ。当時の日本企業が海外でプレゼンスを拡大し、日本人ビジネスマンが慣れない異文化と格闘しながら仕事に没頭する。その一方で、彼らの個人的な情動はどう処理されていたのか。豊のようなエリート社員が仕事の合間、あるいは仕事の延長線上で手に入れる秘密の恋は、日本が経済成長とともに成熟していく過程で生じる社会的ひずみを象徴しているとも言える。
また、バンコクという都市は当時から東南アジアの中心的存在であり、国際ビジネスが盛んな一方で、独特の風俗や文化を持ち、欧米とも日本とも異なる情緒を湛えている。この都市選択は、単にエキゾチックな舞台を求めたものではなく、作者および映像化スタッフの狙いとして、日本的価値観から一旦離れた空間を用意することで、人間関係や道徳的規範が相対化される効果を生み出している。バンコクは、愛が芽生えるための無国籍空間として機能し、登場人物たちの感情はそこでは純粋な欲望と悲しみ、孤独と希望を伴って解放される。
不倫を扱う作品は数多く存在する。国内外の文学や映画にも、不倫を題材とした名作は多い。例えば、日本文学においては谷崎潤一郎や三島由紀夫といった耽美的作家が、禁断の恋愛や歪な欲望を描くことで、人間の内面に深く切り込んできた歴史がある。海外では、例えばグレアム・グリーンなどが、異国を舞台にした恋物語を通じて、人間性や信仰、倫理観を問い質してきた。『サヨナライツカ』もまた、この伝統の中に位置づけることができるだろう。不倫という社会的タブーを通じて人間性を浮き彫りにする作家たちの系譜の中で、辻仁成は自らの文学的感性を注入することで、新たな「愛の形」を探求した。
ただし、『サヨナライツカ』は単純な耽美主義や悲恋物語に終始しない点で特徴的だ。物語は「いつか」や「さよなら」という言葉が示すように、必ず終焉に向かって突き進む。それは、読者や観客に対して「この関係は一体何だったのか?」という問いを残す。もし不倫が単なる背徳行為だと断じるなら、登場人物たちは倫理観に反した愚行者として批判されるに過ぎないだろう。しかし、物語が終わった後、観客は彼らが感じたであろう幸福や刹那の輝きが、それほど軽々しく否定できないものであったことを知る。そこには、不倫という題材があらかじめ内包する緊張関係と同時に、人間がいかにして「生」を実感するかという普遍的テーマが潜んでいる。
愛とは何か?欲望のその輪郭
不倫は、当時も今も、道徳的には肯定されがたい行為である。その点で、本作は観客に不安定な道徳的立場を要求する。しかし、同時に不倫の関係にある二人が生み出す感情や体験は、時代や文化を超えたところで理解され得る。1970年代は今から約半世紀前であり、その間に世界は大きく変化した。不倫に対する社会的な見方も多様化し、必ずしも白黒はっきり断罪されるものではなくなってきている。それでもなお、本作が示すのは、人間の根底にある欲望の普遍性である。どれほど社会が変化し、通信が発達し、グローバル化が進んでも、人は自分の心が求めるものに抗えない瞬間がある。それが倫理に反し、理性に背く行為であったとしても、そこには何らかの人間的真実が宿る。
このような人間的真実の追求は、不倫を扱う多くの作品が試みてきた課題でもある。だが『サヨナライツカ』は、1970年代バンコクという異郷を舞台とすることで、その問いをより鮮明に提示することに成功している。異国での恋は、文化的背景や常識が異なるため、より純粋な情動の力学が浮き彫りになる。豊は日本でなら従うべき常識や慣習をバンコクでは一旦脇に置き、沓子はその奔放な魅力によって、彼を社会的存在から一個の人間へと戻す。ここに不倫というテーマ以上に、人間がどのようにして自分らしさを取り戻すかという問いが隠されている。豊と沓子の関係は、愛情という名のうきわ(浮輪)を掴むことで、自分たちが溺れそうになっていた人生に一縷の活路を見出そうとする行為にも見える。
時代背景にも注目するなら、1970年代は日本が高度成長を経て、国民全体が豊かさを享受し始めた時代である。しかし物質的豊かさと内面的充実が必ずしも一致しないことは多くの文学者や思想家が警鐘を鳴らしてきた。『サヨナライツカ』の中で描かれる不倫は、その満たされない心の隙間、あるいは社会的成功者であるがゆえに生じる虚無への抵抗とも言えよう。豊かになったはずの社会のなかで、なぜ人はまだ他者を求め、禁断の愛に走るのか。ここに、作者の辻仁成が当時の日本社会、あるいは現代に至るまで継続する人間の本質的な葛藤を映し出していることが窺える。
映画においては、映像表現の美しさも本作の大きな魅力だ。バンコクの街並みやホテルの内装、熱帯地方特有の湿度感、時折差し込む光と影のコントラストが、二人の関係に妖しくも美しい彩りを添える。小説では文字で描かれていた感情が、映像作品では色彩や構図、音楽によって異なる感覚的インパクトを生む。そうした感覚的な要素は、観客の理性による判断を一瞬麻痺させ、豊と沓子の愛が果たして善か悪かという単純な価値判断を困難にする。絵画的な美しさを帯びた不倫描写は、時代背景や社会的文脈を踏まえた批評的な眼差しを同時に要請し、作品の評価を単なるエロティックなメロドラマに落とし込ませない。
さらに、本作の特徴として作者が元々ミュージシャンとしての活動経験も持つ辻仁成のバックグラウンドが影響している可能性もある。音楽家出身の彼は、しばしば言語表現に音楽的なリズム感やメロディーラインを持ち込み、官能的な感性を物語構築にも活かしてきた。『サヨナライツカ』では、その感性が異国情緒と不倫という禁欲的なテーマと結びつくことで、独特のリリシズムが流れ込む。愛欲と後悔、予感と不安、快楽と苦痛といった相反する感情が作中を満たしていくさまは、一種の音楽的交響曲のようでもある。これらの要素が映画表現と融合することで、観客は言葉以前の直感的なレベルで作品を味わうことができる。
チャレンジする人間、継続不能な試み
当時の不倫に関する作者のアプローチを語る上で重要なのは、作者が必ずしも不倫を肯定したり、浪漫化したりしていない点だ。むしろ、『サヨナライツカ』が示すのは、不倫という行為が必然的に喚起する悲劇性や矛盾である。倫理的に赦されない行為であるがゆえに、そこに展開される愛は持続不可能なものであり、刹那的な美しさを帯びる。その刹那を掴もうとする人間は、自らの手で自分を傷つけながらも、求めずにはいられない。これは他の不倫文学にも共通する性質だが、本作はそれを1970年代のバンコクという、ある意味で制約された時代・場所によって際立たせる。まだ国際線のチケットが高価で、通信手段も限られ、情報が即座に手に入らない時代に、不倫関係が育まれる背景には、現代には失われた空間的・時間的余白が存在した。作中、豊と沓子は、その余白の中で純度の高い感情を交換し、その結末として避けられない別離が訪れる。
当時と現在を比較すれば、不倫を取り巻く社会意識は大きく変化しているかもしれない。現代ではSNSやメディアで有名人の不倫が大々的に報じられ、一般人も倫理観の変化を受け止めつつある。しかし、このような背景があっても、『サヨナライツカ』が描く愛の形は、単純に今の価値観で裁かれるべきではない。むしろ、異なる時代・異なる場所で紡がれた物語だからこそ、そこに刻まれた愛の模様は、現代を生きる私たちにも新鮮な問いを突きつける。なぜ人は禁じられた愛に惹かれるのか、なぜ社会的成功や安定を手に入れながらも、なお心は満たされないのか。これらの普遍的な問いが、作品を時代や場所を超えた存在へと押し上げている。
総じて、『サヨナライツカ』という作品は、1970年代のバンコクを舞台に、不倫というタブーを通して人間の本能的欲求、時代背景の影響、そして愛の本質を問う意欲的な試みと言える。辻仁成が原作で築いた文学的世界観は、映画化によって視覚的・聴覚的刺激が加わり、より多面的な鑑賞を可能にしている。中山美穂と西島秀俊が紡ぐ不倫劇は、決して一過性の背徳ロマンスではなく、時代を超えて人々を揺さぶる命題を内包している。
テーマ性のある、投げかけ、人間の深淵
このような批評的視点を踏まえると、『サヨナライツカ』は不倫を扱った作品の中でも特異な位置を占めている。過去の不倫文学・不倫映画がしばしばセンセーショナルなスキャンダル性や悲劇性のみを強調する中、本作は人間存在の深淵に踏み込み、国際化時代の影、異文化交流の軋轢、個人の孤独や喪失感を織り交ぜる。1970年代は、今日のグローバル社会の源流ともいえる時代であり、その時代において形成された愛のかたちは、現代の私たちにとっても意義深い。豊と沓子の出会いと別れは、ひとつの時代を映し出す鏡であり、同時に愛と欲望、喪失と再生という永遠のテーマへと通じている。
不倫というテーマは往々にして後ろ暗く、後味の悪いものとして語られがちだが、『サヨナライツカ』はその暗がりの中から美と真実を掬い上げようとする。倫理的に正しいかどうかは別として、この作品が提示するのは、人間が求め続ける心の安息や魂の救済だ。外界の光と影、価値観の揺れ動く都市空間、言葉に尽くせぬ喪失感、それらが織り成す不倫関係は、単なる道徳的逸脱ではない。それは人間が自分自身の生を証し立てるために掴みとる、一瞬のきらめきなのである。
こうした批評的分析を経て観直す『サヨナライツカ』は、もはや単なるロマンス映画や、不倫スキャンダルに沸く娯楽作品ではないことに気づくだろう。作者辻仁成が描き出し、映画スタッフと俳優たちが形にしたこの物語は、人間が生きること、愛すること、別れること、そのすべてを1970年代バンコクという特異な座標軸で捉え直した、一種の精神史的な記録である。私たちはこの物語を読むなり観るなりする中で、不倫という行為を超えた、より深い人間性の問題に直面する。それは、遠い異国で起こった幻影のような恋物語でありながら、現代を生きる私たちの内面にも響く普遍的メッセージを放っている。
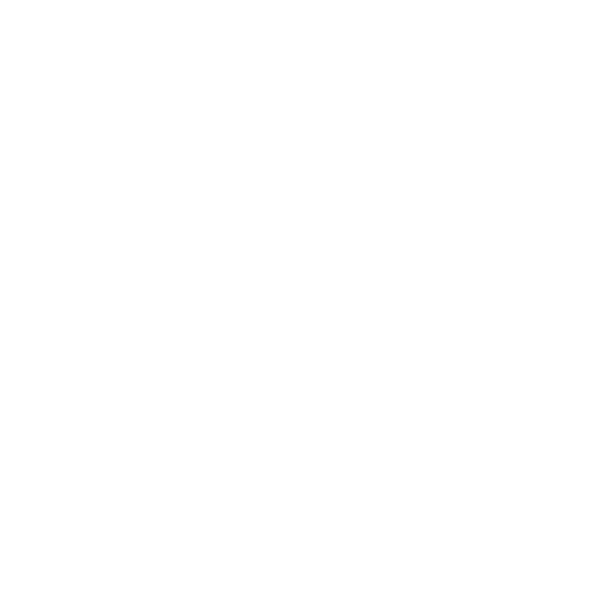



コメント